(2025年8月25日投稿)
こんにちは。中小企業診断士の辻本昂大です。
中小企業診断士2次試験は、合格率が20%前後と難関試験のひとつです。
特に、勉強を始めようと思っている方や、まだまだ勉強中の方は
「2次試験合格には何時間くらい勉強すればいいんだろう…」
「何時間で合格者レベルまで到達できるんだろう…」
と不安になることが多々あると思います。
そこで今回は、中小企業診断士2次試験に一発合格した筆者が
必要な勉強時間を解説し、皆さんが合格までの道筋をイメージできるようにしていきたいと思います。
更に、「仕事や子育てが忙しくて…」という皆さんに向けて
また、「まとまった時間が取りにくい」という方に向けて
「事例ごとに必要な勉強時間はどれくらいだろう」という方に向けて
本記事ではこれらの疑問を解消していきます!
クリックで気になる部分にとぶことができますよ!
中小企業診断士2次試験の特徴と難易度
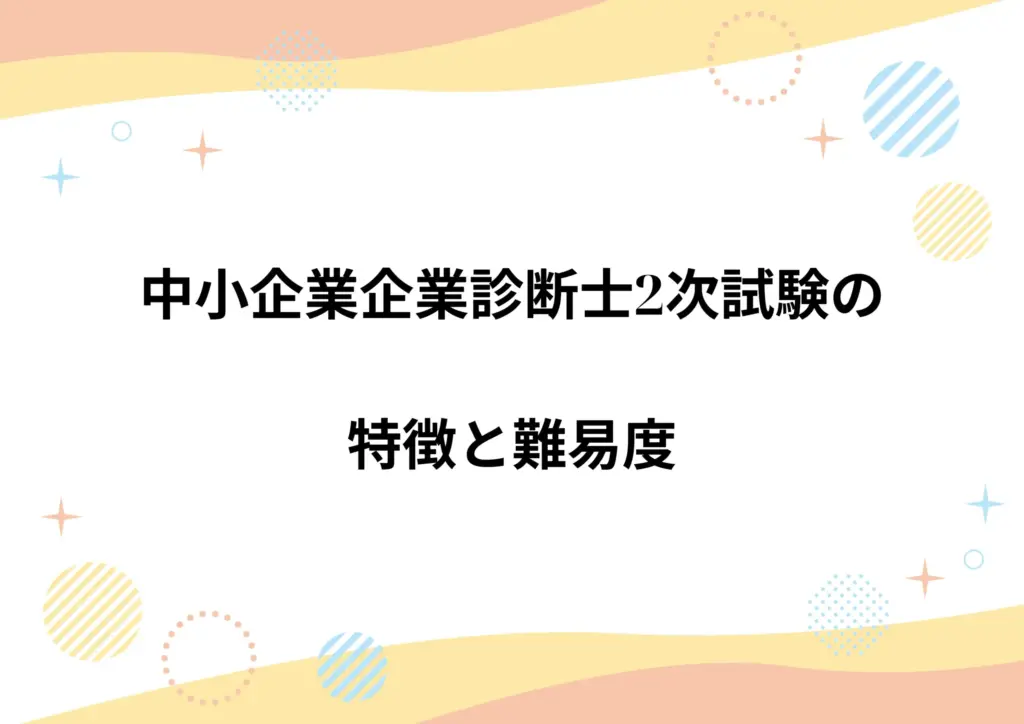
1次試験との違い
1次試験との最も大きな違いは「インプット型」から「アウトプット型」の試験に変化することです。
具体的に説明します。1次試験は7科目という膨大な試験範囲を暗記し、選択式という単純な形式の問題を解答します。
明らかにインプット部分の比重が重い試験になっています。
逆に、2次試験は与えられた事例に沿って、自身の持つ知識や思考を応用させながら解答を組み立てていきます。
事例を上手に解くには、「中小企業診断士としての思考」を身体に染み付けるための徹底的なアウトプット型の勉強が必要になります。
合格率と合格者像
合格率は約20%前後、例年ほとんど変わりません。
それは、中小企業診断士2次試験が相対評価に基づく合格基準が設定されているためです。
つまり、1次試験を勝ち抜いた5人の内1位にならないと合格できないということです。
とは言っても、そんなに気負う必要はありません。
ある条件をクリアできれば、それだけで上位40%に入ることができる。そんな条件があります。
それは、「勉強時間をしっかり確保する」です。
まあ、当然のことなんですけれど。
受験者は社会人が多く、意外と勉強時間を確保できないまま2次試験を受験される方が多いです。
で、曖昧な知識と練度のため散っていきます。
なので、何が何でも勉強時間を確保できただけで合格率は倍以上に跳ね上がります。
試験が「実力勝負」と言われるは正しいのか?
よく、中小企業診断士1次試験が「努力量勝負」2次試験が「実力勝負」と言われます。
2次試験は分析や表現力が求められるということから、巷で噂されるようになりました。
ですが、私は少し違うのかなと感じてます。
実は、私丸暗記型の人間で、表現力や思考力が全くの苦手でした(診断士としてどうなんだってとこはありますけど、、)。
受かるためにやったことが、徹底的に事例問題の解き方を身体に叩き込みました。
応用力や創造性のない私にとっては、中小企業診断士の事例を解く思考過程を、暗記力でトレースする。
このようなやり方も十分アリです。
決して実力(センス)だけの試験ではないのです。
合格に必要な勉強時間の目安
合格に必要な勉強時間の平均や、具体的に算出した最低ラインを紹介します
合格者の平均勉強時間(300時間~500時間)
合格者の平均勉強時間は約400時間と言われています。ボリュームゾーンとしては300~500時間程度でしょう。
ちなみに、一発合格することができた私はというと、300時間強でした!
周りの合格者の方々は、多年度勢生や一発合格生で多少違いはありますが、だいたい300~600時間の方が多いイメージです。
最低ラインは300時間程度(事例ごとに紹介)
2次試験を安定して確実に合格するための最低ラインは300時間です。理由は2つあります。
1つ目に、事例Ⅰ~Ⅲで安定した得点を積み重ねることができるようになるまで150~200時間必要です。
事例1年度分を復習も含めて解こうとすると2時間、それを3科目×7年度×3回×2時間で約120時間必要になります。
そのほか、情報収集やFP(ファイナルペーパー)を作成する時間も見積もると150時間程度は必要でしょう。
2つ目に、事例Ⅳを確実に得点するには150時間は必要です。
事例Ⅳは会計問題になっており、範囲自体はそこまで広くありませんが、簿記1級レベルの問題ばかりが出てきます。
しかし、この事例Ⅳ最も安定的に高得点が取れる科目なんです。
会計知識がない人がそのレベルに達するまでに、
基礎知識の理解→基礎問題演習→応用問題演習→NPVの総仕上げ、のような手順を辿り、何度も繰り返し問題を解く、
とすると150時間は必須でしょう。
これら2つを合計して300時間は必要という計算になります。
1次試験直後から始めた人と多年度組の違い
1次試験直後から始めた人と多年度組の最終的な違いは、8月のスタートラインでのレベルが違うことくらいなのかなと思っています。
活用できる過去問の量も決まっていますし、教材も良質なものは、ほぼほぼ固定されています。
ただ、試験対策のプロセス上では明確な強み弱みも存在しており、以下で紹介します。
多年度組の強み・弱み
1次試験直後組の強み・弱み
私の勉強時間の確保方法
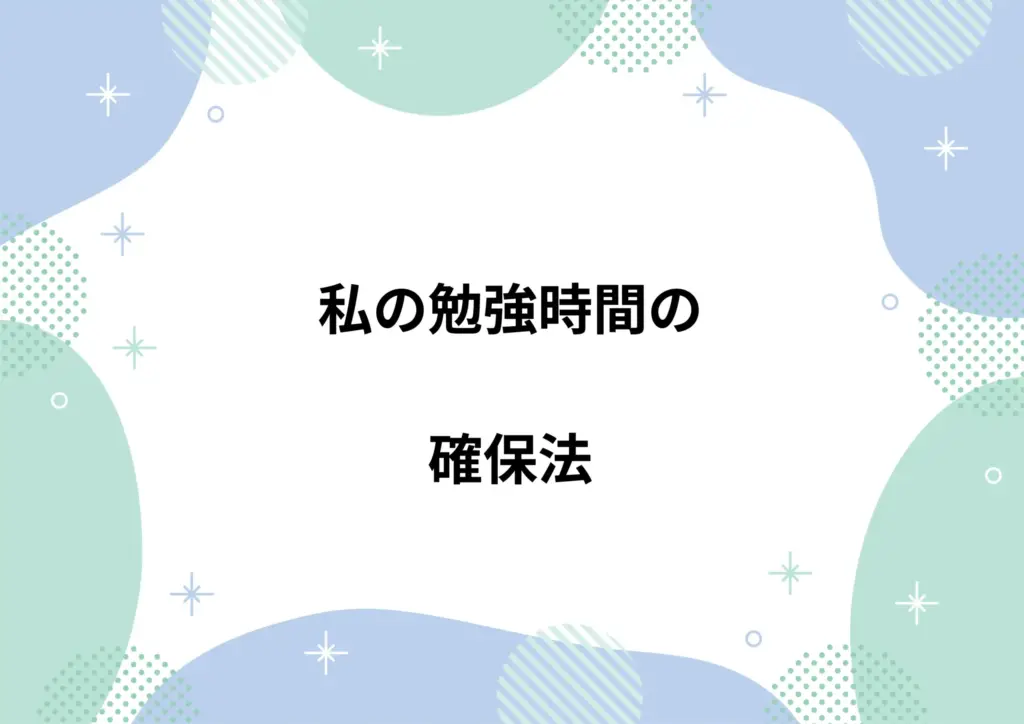
私は、仕事では幹部自衛官を続けながら、家庭では子供もいましたが、2次試験を合格しました。
勉強期間の中に大きな訓練があり、山に1週間以上籠りっぱなしの時がありました。
それでも3ヶ月で300時間以上確保できた方法を紹介します。
平日・休日の勉強時間モデルケース
平日の勉強は基本的に早朝、出社前にまとまった時間を確保しました。約3時間程度です。
人間の脳は朝最も活性化されること、そして早朝こそ誰からも干渉されず事例問題を解くことに集中できるからです。
基本的に、夜9時には寝て、3時頃起きて勉強していました。
夜勉強していた時期もあるのですが、仕事終わりは眠すぎて話になりませんね。
ただ、体力勝負になるので通年では続けられません。
休日の勉強では日中は全て勉強の時間に充てていました。
10時間くらいですかね。2次試験は特にまとまった時間が取れる休日が勝負です。
本当に受かりたいなら、なるべく予定は入れずに、夜家族サービスするつもりで、日中は全て勉強に使った方がいいです。
家庭や仕事と両立した勉強時間の確保方法

社会人として、勉強時間を確保するためのボトルネックになることが多いのが、仕事との両立、家庭との両立です。
ここで、私なりの仕事と家庭への付き合い方をご紹介します。
仕事はやはり「上司の理解」が一番重要なのかと思います。
私は、資格の有用性や熱意を説いて、何とか上司には理解してもらったおかげで、勉強時間の確保で融通を利かせていただきました。
それができない方でも、定時やなるべく早くに退社できる環境を、無理を押してでも整えていくことが重要です。
家庭は、様々な形があると思いますが、一番ボトルネックになる方が多いのが、お子さんと奥さんの存在でしょう。
私もまだ小さい子供がいます。家族サービスやお世話が必要な時期でした。
しかし、資格取得は将来の家庭を守るため、また自分自身のやりたい仕事のためであることを根気強く毎日語り、協力体制を敷いてもらうことができました。
勉強できる環境を整えることは、合格のための重要な「前提」になってきます。
最短合格者の時間の使い方
時間の使い方で最も意識したことが、すべての勉強時間を計測するということです。
これは、問題を解く時間だけでなく、復習や解答確認をする時間も含めます。
この方法の、何が最短合格に繋がるかというと、
1点目が、試験の本番時間に対応しやすくなるということです。
1次試験と異なり、2次試験は制限時間が非常にタイトです。
この時間感覚になれることが安定した回答を作り上げる需要な要素になります。
2点目に、メリハリのある勉強ができるということです。
2次試験は表面だけでなく、事例に対する深い思考が求められます。
マンネリ化した勉強ではなく、時間を決めて問題の深い部分まで考え抜かなければいけません。
深い思考のためには、毎回時間を決めて取り組んであげることが重要になります。
科目別の詳しい勉強時間は?
まとめ:勉強時間は合否を左右する重要なキー
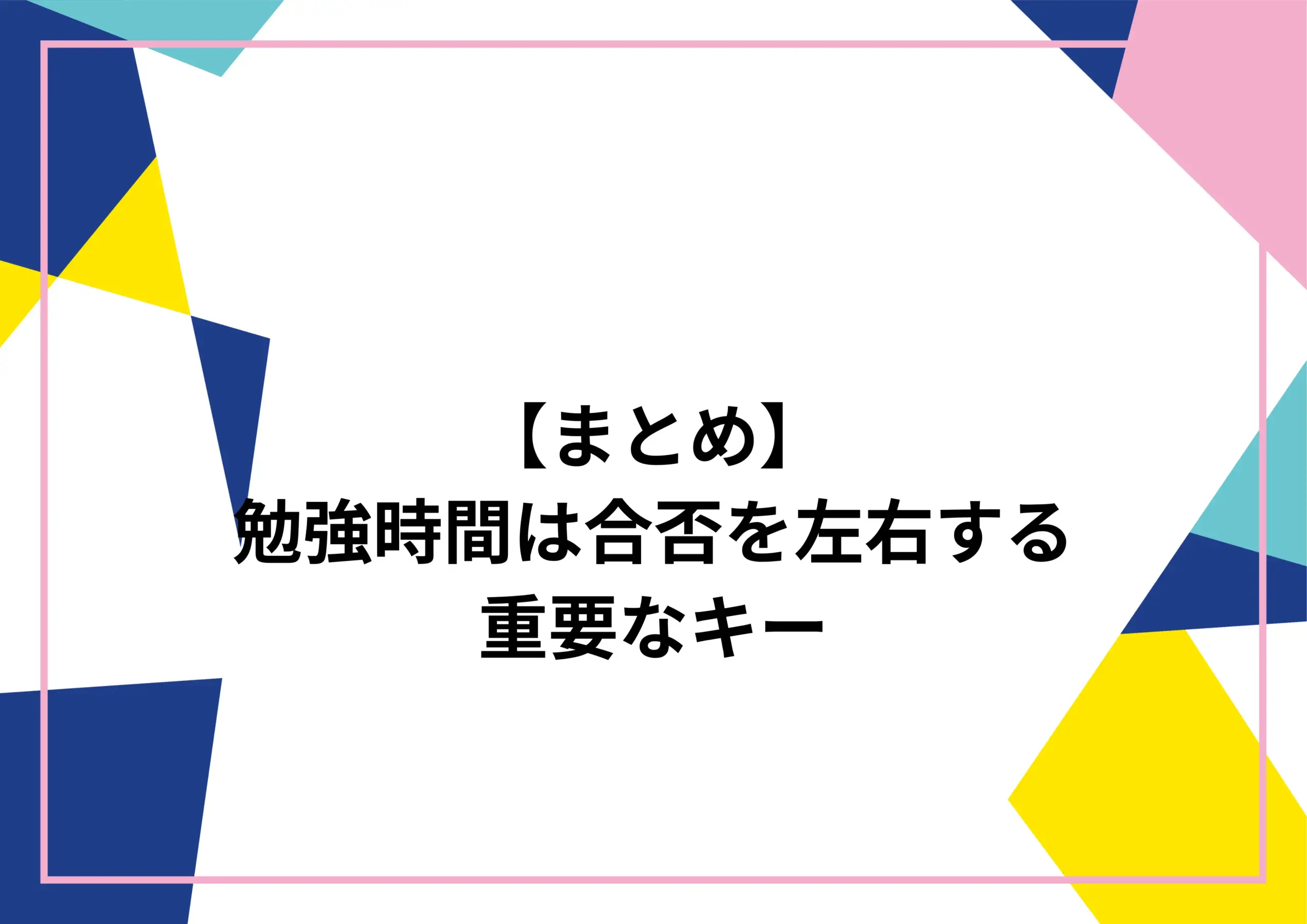
皆さん、中小企業診断士2次試験の勉強時間について理解していただけましたか。
中には200時間や150時間で合格した!という方はいますが、
ゼロベース(会計知識もコンサル経験も無い)状態での試験対策は300~500時間かけないと安定した合格は望めないでしょう。
本文でもお伝えした通り、
十分に勉強時間を確保して、満足に試験勉強をできた方はそれだけで上位40%に入っていると自負してもらって大丈夫です。
それだけ、仕事と家庭を両立して勉強時間を確保するのは難しいことです。
しかし十分に勉強時間を確保できた時は、合格可能性を手繰り寄せることができるでしょう!
ぜひ頑張ってください!




