(※2025年8月27日に投稿)
こんにちは、中小企業診断士の辻本昂大です。
中小企業診断士の2次試験は、1次試験とはまったく性質が異なり、
“事例を読み解き、論理的に答案を組み立てる力”が試される実力勝負の試験です。
独学で挑む場合、
「1次試験と内容が違いすぎてどこから手を付けていいかわからない…」
「問題が難しく自分にも解けるかわからない…」
と不安を抱く方も多いでしょう。
本記事では、
独学者向けに
“戦術的な2次試験対策の勉強法”
“中小企業診断士2次試験の本質”
を徹底解説します。
著者である私は元自衛官として戦術的な思考法を身につけてきました。
その経験を応用し、効率的かつ戦略的に対策を進めるための方法もお伝えします。
中小企業診断士2次試験の本質を理解する
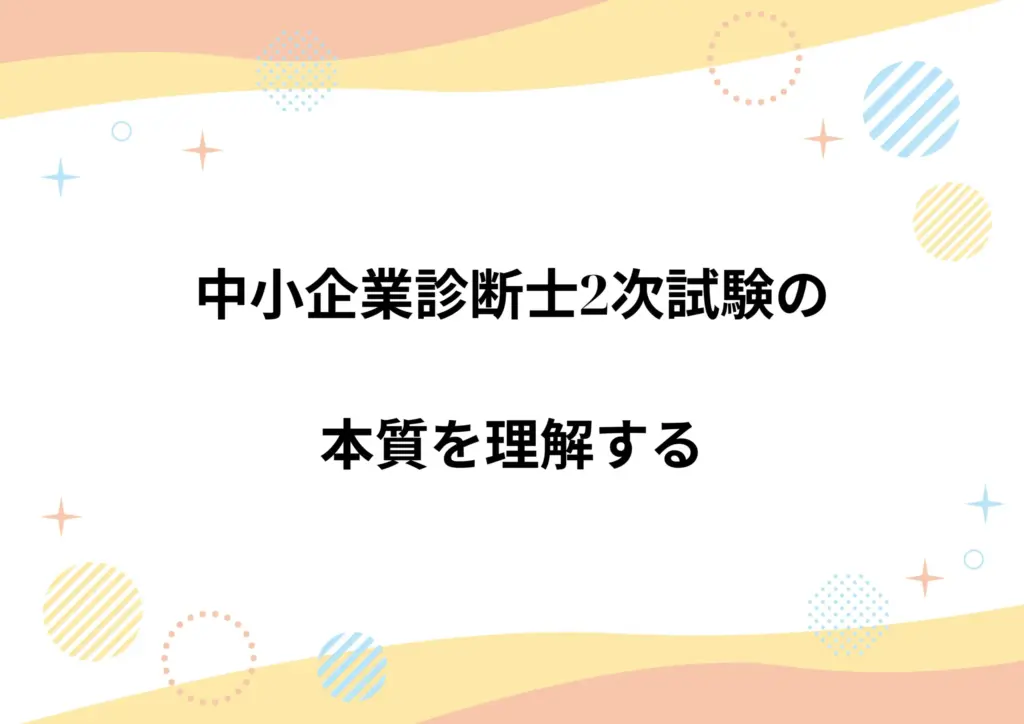
対策の第一歩は、2次試験は中小企業診断士になるために、どのようなことを問われているのか。
という本質を分析することです。試験内容には必ず意図があり、それを満たしてあげることが合格に繋がるのです。
自衛隊でも戦闘が始まる前に、戦場を徹底的に研究したり、敵の行動パターンを洗い出していく各種見積は徹底的に行います。
勉強を始める前に深くまで2次試験を分析してみてください。
暗記型試験(1次)と事例型試験(2次)の違い
1次試験との最も大きな差は、
2次試験が与えられた与件文(診断先会社の実情)を基に、分析・アドバイスしていく、事例型の試験であるということです。
2次試験対策を始めたばかりの方はこの違いに大いに戸惑うことでしょう。
また、事例Ⅳも問われる会計知識が簿記1級並みとなり、より複雑な問題が出題されます。
そこで、ブログの下記項目では2次試験に特化した対策を紹介します。
2次試験はあなたの思考力を試される
2次試験の採点基準は中小企業診断士庁より発表されていません。
それはひとえに、2次試験が知識だけでなく、「思考力」を採点される試験だからです。
知識の部分は、1次試験で十分にクリアしています。
しかし、診断士として問題解決をこなしていくためには、
“通常の人(それこそ支援先企業の誰もが)が持ちえない、問題解決思考ができる”必要があります。
これを、採点するにはどうしても明確な採点基準は設けられないのです。
2次試験はキーワードによる採点か⁉
しかし、採点者にとって大まかな採点基準は存在していると考えられます。
それは、採点者が全員同じ感性や思考を持っているわけではないため、公平性を確保するために必要となります。
では、どのような採点基準でしょうか。
それは、キーワードによる採点基準である可能性が高いです。
キーワードと言っても、与件文の抜き出しではなく、“論理的思考の末にたどり着く文言”とでも言いましょうか。
ある程度、与件文がリードしてくれるので、診断士的思考がしっかり身についた方は同じような答えに行きつきます。
その、答えがキーワードとして採点されているのではないかと予想します。
そのため、ふぞろいを使ったキーワード対策は非常に有用であると言えます。
独学で挑む2次試験対策の基本戦術
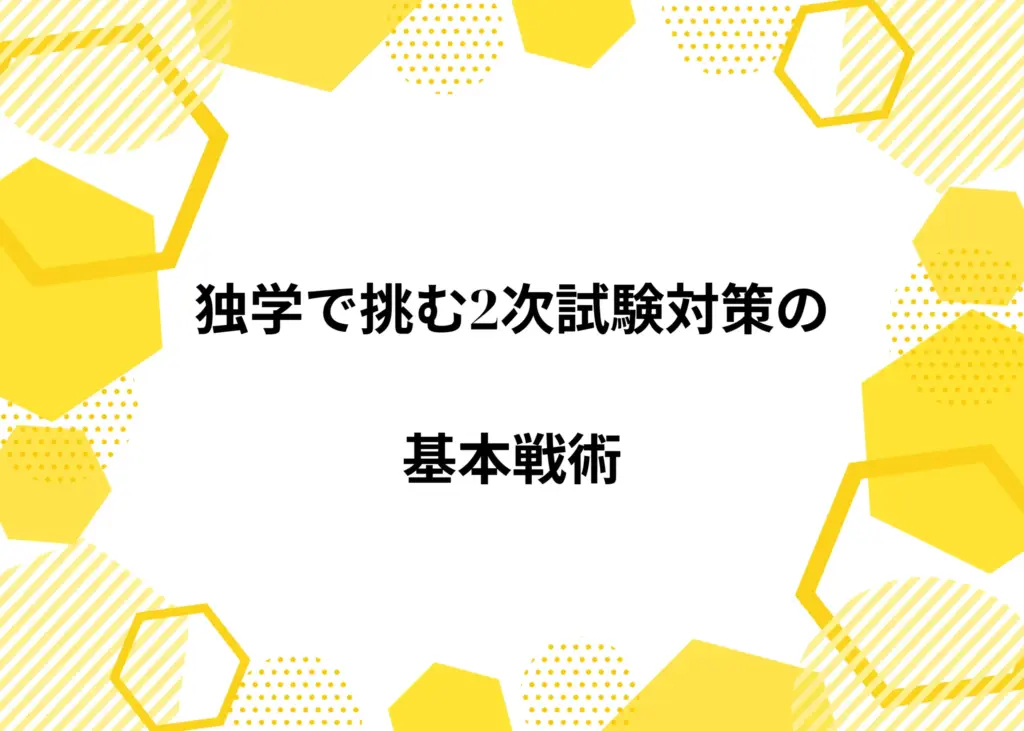
独学で挑む際、最も重視してほしい対策の3本柱が、
①過去問を軸にした学習
②答案の型を身につけること
③事例Ⅳを徹底的に対策する
です。それぞれ解説していきます。
過去問演習を軸にした学習
中小企業診断士2次試験の学習教材はかなり特殊で、過去問を取り扱っている教材で対策するのが最も効果的です。
理由はいくつかありますが、、
①受験者数が少ないので力を入れた対策本がすくない
②トレンドの事例問題や中小企業に重要な会計知識が問われる試験なので代用できる教材が少ない
といった理由が主で、過去問を軸にすることが最も勉強効率が良いです。
模試とかもいいんですけど結局予備校が作ったものなので信憑性は過去問より低いです。
具体的に、どの教材がいいの?と疑問に思われたと思います。
私のおすすめを紹介します。
まず事例Ⅰ~Ⅲはふぞろいで決定です。
最新版の「ふぞろいな合格答案」と過去6年は網羅できる「ふぞろいな答案分析」を揃えてください。
逆に、過去6年度以前は問題傾向が結構変わっているので、演習しても逆に混乱するかなと思いました。
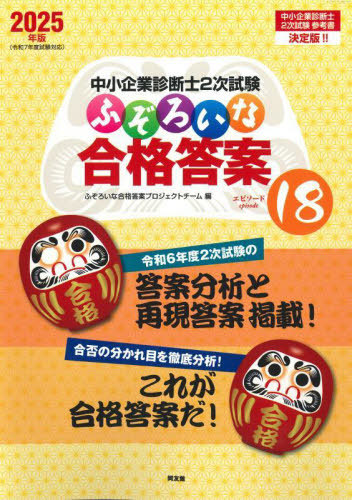
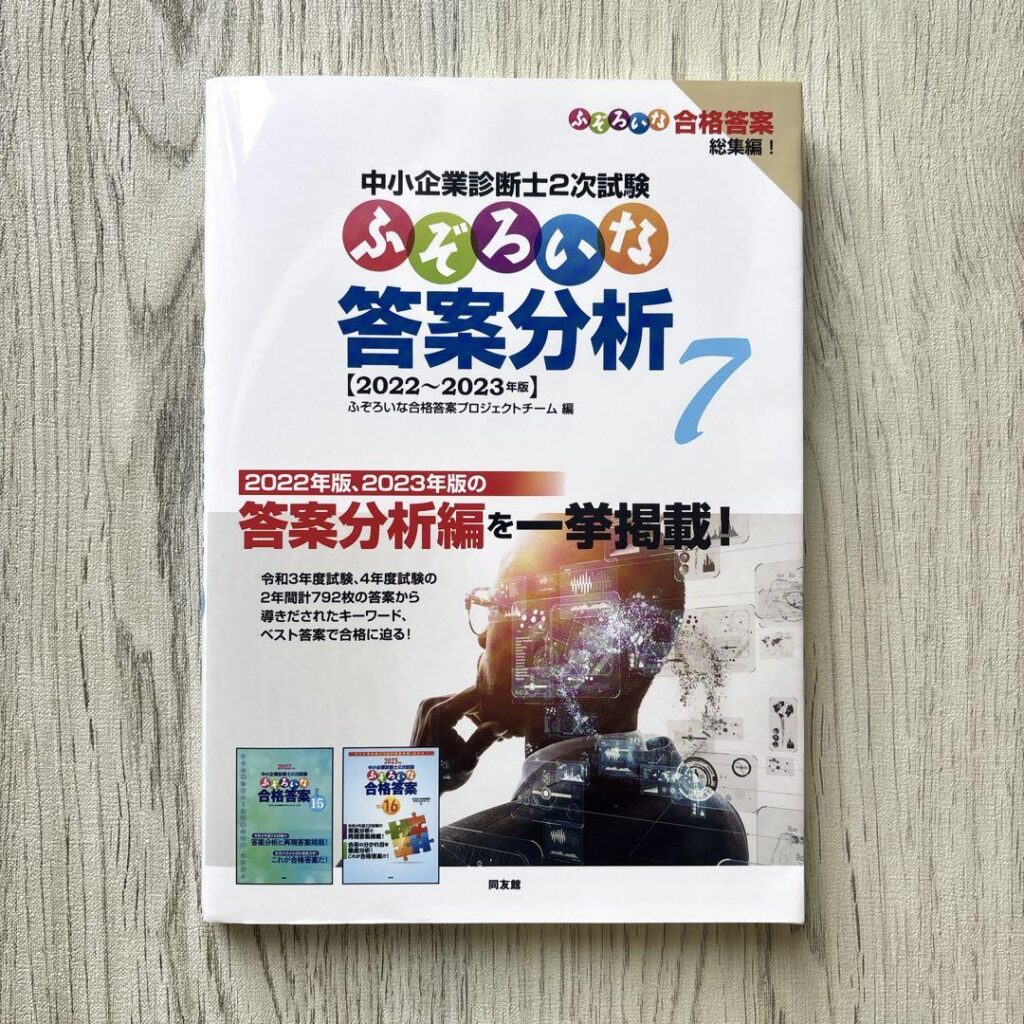
事例Ⅳは「事例Ⅳの全知識全ノウハウ」が最も良質です。
会計問題は、トレンド等で変わらないため、収録の年度分をすべてやり切ってください。
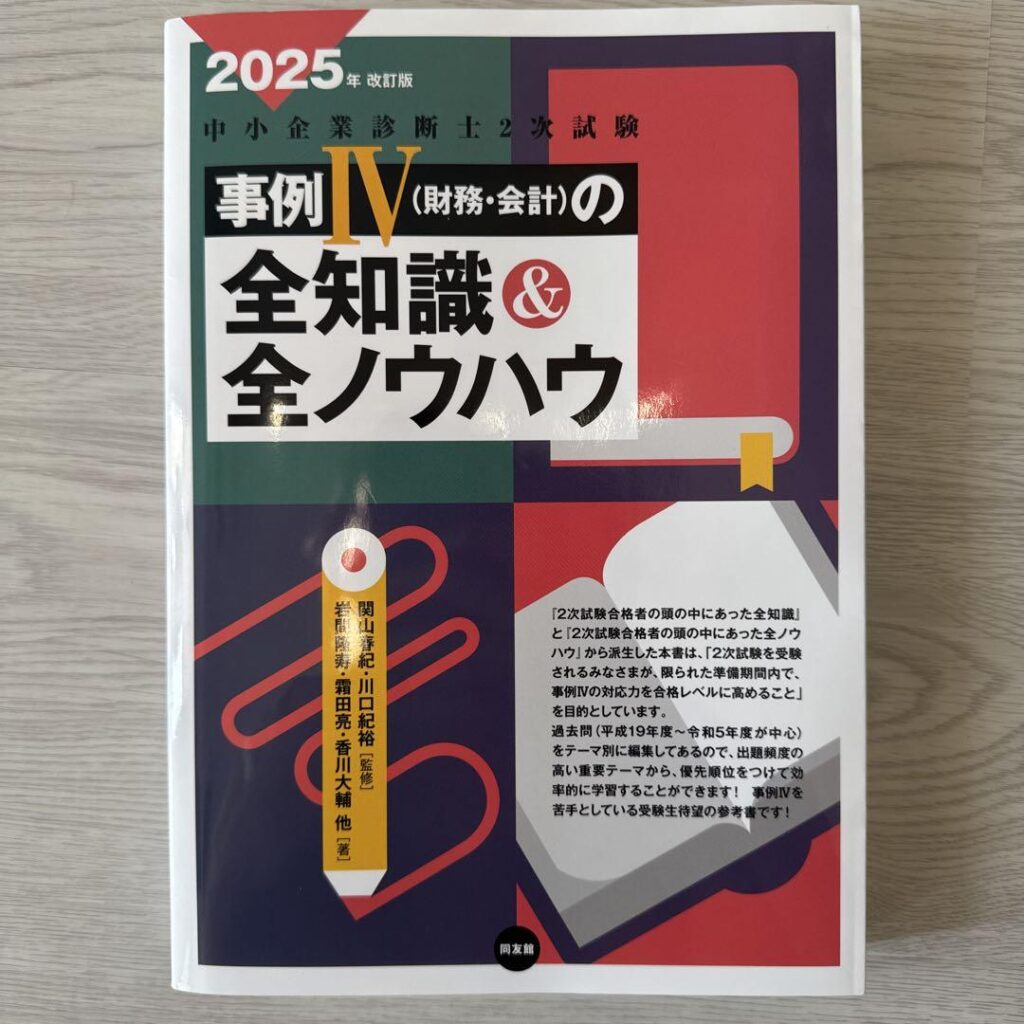
これらの詳しい使い方は別の投稿で解説しますね。
解法の型を身につけることの重要性
これは主に事例Ⅰ~Ⅲに当てはまる対策になります。
2次試験は試験時間がとても厳しく、ほとんどの方が終了ぎりぎりまで足掻くことになると思います。
このような、試験で最も安定的に得点を積むには解法を「標準化」する必要があります。
2次試験でみんな大好き標準化ですね。
そこで、解法も標準化してあげることで最速最適に与件文にアプローチできるようになるということです。
例を挙げると、
①SWOT分析手法の確立や
②フレームワークの活用
③FP(ファイナルペーパー)等です。
この他にも細かいものはたくさんありますが、基本的には過去問を解きながらあなた自身の解法を最適化していくイメージになります。
自衛隊でも、訓練による標準化を身につけて、最速で安全に戦闘行動できるようにします。
解法を体に染み込ませることは、戦術的にも理にかなっています。
事例Ⅳの徹底的な対策
実は2次試験対策で最も重要な肝が事例Ⅳ対策です。
よく、事例Ⅳを制する者は2次試験を制すると言いますが、まさにその通りです。理由として、
- 出題範囲が限定的であること
- 50点分以上は出る論点が固定(経営分析とNPV)
- 事例Ⅳは得点調整で最も点数が伸びやすい
この3点の理由から、問われる会計知識が簿記1級レベルにも関わらず、事例Ⅳが最も対策しやすい科目なのです。
戦術的にも、戦闘の緊要(最も重要な)場面に対し、戦闘力を集中するという考え方があります。
最も重要な科目に力を入れるのは当然のことです。
では、過去問以外でどのように対策するのか。
簿記等の会計系資格を取られたことのある方はイメージがつくと思いますが、多くの論点が詰められた問題を大量に解くことです。
どういう問題かというと、いくつものテクニックが必要になる、難易度の高い問題のことです。
事例Ⅳの問題はアウトプットが最も重要かつ、質の良い(様々な論点が詰まった)問題を解くことで爆発的にレベルアップすることができます。
簿記1級の教材や「意思決定会計講義ノート」を使うことで、より質の良い対策が可能です。
是非皆さん、事例Ⅳ対策は全力で取り組んでください。
独学の限界を補うためのリソース活用
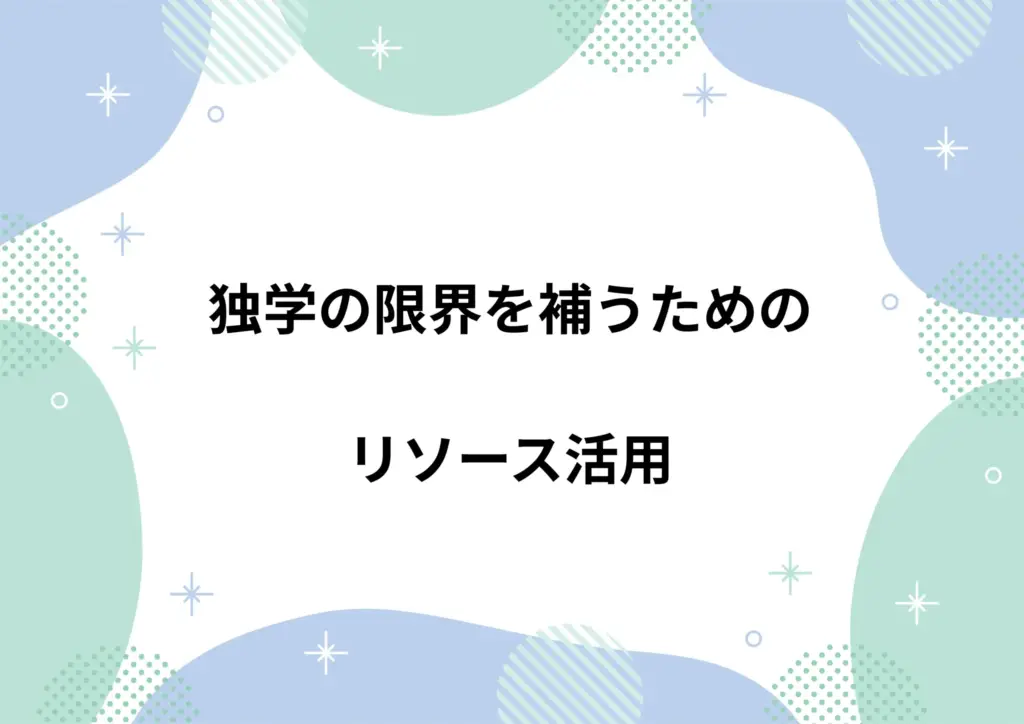
独学で勉強を進めていると様々な悩みを抱えることになります。
「自分の勉強法はあっているのかな」
「添削してもらいたいけどお金がかかるな」
「情報交換してみたいな」
そんな独学者の悩みを解決するツールたちを紹介します。
徹底的にAI対策を活用

近年、最も対策として注目を集めているのがAIによる2次対策です。もう完全に人間の思考力を超えてきており、思慮深い模範解答を提示してきてくれます。
使い方として考えられるのは、事例Ⅰ~Ⅲの
①回答の添削、
②問題の作成
③与件文の解説、
④使えるフレームワークの抽出
等、活用方法はいくらでもあります。
では、どのAIがおすすめなのか、
「Gemini 2.5 Pro」(2025年8月時点)が一番活躍してくれるでしょう。
特定分野ごとのキーワードの抽出や、日本語での文章表現が一番優れており、「質問者が見たい回答」を最も正確に出してくれます。
来年以降の受験生には必須ツールですね。有料版に課金しておいて損はないです。
実務補修でも使うことになりますし、、
戦術的に見ても最新技術の現場適用は敵軍との大きな有利点になりえます。
ただし、フェイク情報を返してくる可能性もあるので、あくまで補助としての活用にとどめておいてください。
気をつける部分はありますが、AI対策が確立していない今ですと、他の受験生との大きな差別化ポイントになるでしょう。
活きた情報を集めるにはXを始める
AIでなかなか対策しにくい部分が「活きた情報」を集めるということです。
これらを収集するには、Xを始めるのが手っ取り早いでしょう。
例えば、他の受験者の教材であったり、フレームワークであったり。
意外と試験対策に直接活かせるコンテンツや知識が発信されています。
受験生仲間をフォローしていってください。仲良くならずとも、有益な情報を発信している方はたくさんいます。
特に、最近ではAIを使った対策が議論され始めているイメージですね。
まとめ:独学でも戦術的に対策すれば合格できる
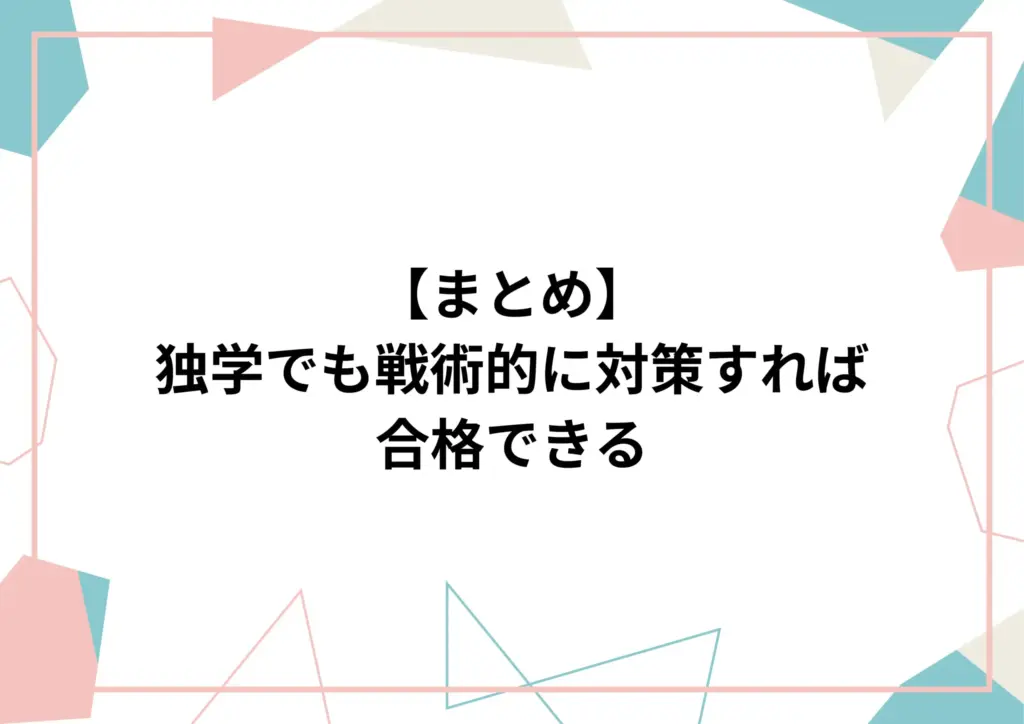
これらの対策を駆使すれば、独学でも十分に一発合格は狙えます。
今回特にお伝えしたい部分としては
“事例Ⅳ対策を徹底的にすること”
“AI対策を活用すること”
の2点になります。
紹介した対策をぜひ念頭に置いてもらって試験勉強を頑張っていただけたらなと思います。




